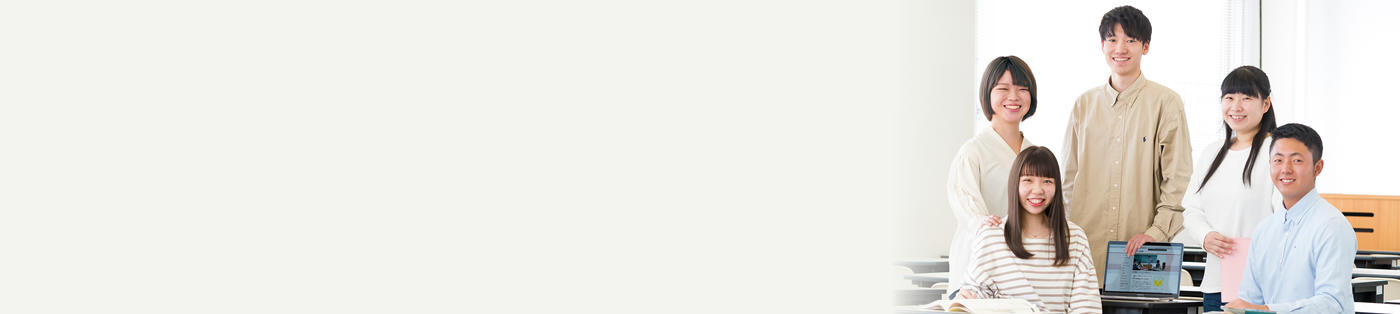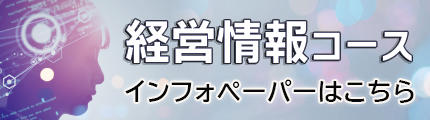医療福祉・マネジメント学科
情報を用いた教授方法の検討とその認知的評価
情報を伝える側と受け取る側、双方の認識の違いに着目
授業にて、ある試験の結果について今まで行ってきた特定の試験との比較は、教わっている学生がそもそも別集団のため、簡単にはできません。同様に診察においても、同じように説明をしても不安な状態にある患者には通常時と同じように正しく伝わるとは限りません。
このように、授業(教師と学生)や診察(医師と患者)といった、情報を伝える側と受け取る側との認識の相違に注目し、従来の教授方法を認知的に評価することで、新たな知見を得られるのではないかと研究を行っています。

関連職種連携教育の授業に参加した時、学生たちがデータ上の模擬患者を実際の患者として想定し、真剣に患者を救う方法を話し合っていました。その光景を目にして、私は、学生たちが「患者の気持ちを考える」「患者の命や生活を救う」という思いを無意識のうちに持ちながら学んでいるのではないかと感じました。また、医療従事者やそれを目指す学生には、他の職種に比べて想像力を含む感性が豊かであり、近年の医療現場で「物語に基づいた医療(NBM)」という考え方が注目されているように、そうした認識や感性が医療現場において必要不可欠であるのではないかという感想がきっかけで研究を始めました。
研究では、情報を教える人物とそれを受け取る人物との間の事例を作成し、関連するワードや理解度をもとに基礎情報(評価値など)を調査し、情報を教える側がどの程度相手の感情を意識しているか、情報を受け取る側の感情について既存の評価尺度を用いて調べています。危険が予測される場面を想定した場面でどのような印象を持ったかを、共感性や他者尺度を使って評価する実験を行いました。その結果、危険を予知するトレーニングを通じて、危険への気づきと「他者の気持ちや状況を想像する」能力(他者尺度)が向上することが分かりました。この研究から、単なる気づきの有無ではなく、評価尺度を加味することで、新たな判断材料を見出せる可能性が示唆されました。

現在、ある条件と既存の尺度を用いた研究を行っていますが、将来的にはより汎用的に用いることができる手法や尺度を導き出すことをめざしています。また、事例作成を進めるために共同研究者を募り、研究をさらに発展させたいと考えています。
高校生の皆さんへ
研究は、ふとした疑問から始まります。そして、研究として形にするためには基礎的な知識が欠かせません。大学には他大学にはない多様な専門職種をめざす学生が集まり、本学科には2つのコースを通じて幅広い知識と分野を学べる環境が整っています。このような環境は、新たな自己発見につながると確信しています。
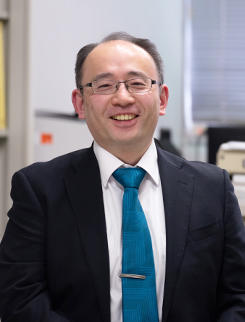
医療福祉・マネジメント学科
診療情報管理・経営コース
江田
哲也
- 専門分野:
- 感性情報学、医療情報学、認知科学
- 担当科目:
- コンピュータの基礎、保健医療情報学、医療統計Ⅰ・Ⅱ、医療情報統計演習、診療情報管理演習Ⅱ、ゼミナールⅠ・Ⅱなど