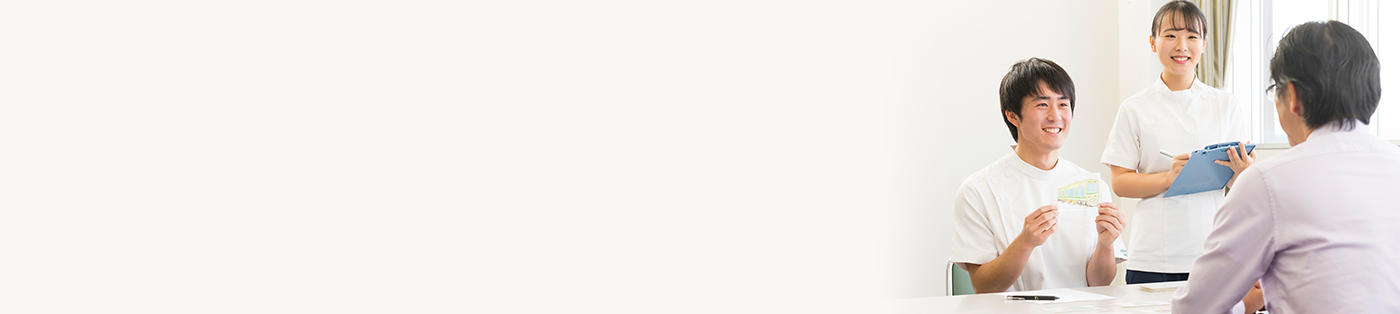言語聴覚学科
学科紹介MOVIE
カリキュラム
| ■失語症学Ⅰ(評価・診断)/Ⅱ(治療)、高次脳機能障害学演習 | 脳血管障害や交通外傷の後遺症で出現する失語症、各種の高次脳機能障害、その他の認知・コミュニケーション障害についてそれぞれの発生メカニズム、評価・診断、治療・リハビリテーションの理論と方法について学びます。 |
|---|---|
| ■言語発達障害学総論/各論 | ことばは子どもの発達が順調かどうかを示す大切なバロメーターです。学習障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害、脳性麻痺などの障害には言語発達の遅れが伴うことが多く、それぞれの症状の特徴や適切な評価・指導の方法を学びます。 |
| ■発声発語障害学総論、摂食・嚥下障害学Ⅰ(理論・評価診断)/Ⅱ(治療) | 成人・小児にみられる中枢性あるいは末梢性の発声の障害、構音の障害、吃音、摂食・嚥下機能の障害について、それらの発現機序、評価・診断の方法、治療・リハビリテーションの方法について学びます。 |
| ■聴覚障害学総論 | 小児および成人において、聴覚がさまざまな程度に障害された場合に生ずる問題を的確に評価・診断することを学びます。 さらに、補聴器、人工内耳、読話、手話など聴覚補償の方法、聴覚障害児・者の発達指導やリハビリテーションの方法を学習します。 |
| ■コミュニケーション技能演習、コミュニケーション障害演習、 言語聴覚障害基礎演習、臨床実習Ⅰ(評価)/Ⅱ(総合) |
専門的なコミュニケーション技能の習得を目指し、段階的に学修します。1年次には、本学関連施設などで、こどもや高齢者とのコミュニケーション技能を学びます。また、コミュニケーション障害をお持ちの当事者の方の講話を直接聴く機会を設け、コミュニケーション障害への理解を深めます。 |
| 科目名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 解剖学 | 必修 | |||
| 生理学 | 必修 | |||
| 病理学 | 必修 | |||
| 医学概論 | 必修 | |||
| 内科学 | 必修 | |||
| 精神医学 | 必修 | |||
| リハビリテーション医学 | 必修 | |||
| 小児科学 | 必修 | |||
| 耳鼻咽喉科学 | 必修 | |||
| 臨床神経学 | 必修 | |||
| 形成外科学 | 必修 | |||
| 臨床歯科医学 | 必修 | |||
| 口腔外科学 | 必修 | |||
| 音声言語医学 | 必修 | |||
| 中枢神経機能学 | 必修 | |||
| 聴覚医学 | 必修 | |||
| 児童精神医学 | 選択 | |||
| 老年学 | 選択 | |||
| 遺伝学 | 選択 | |||
| 脳神経外科学 | 選択 | |||
| 臨床心理学 | 必修 | |||
| 生涯発達心理学 | 必修 | |||
| 神経心理学 | 必修 | |||
| 学習・認知心理学 | 必修 | |||
| 心理測定法 | 必修 | |||
| 言語学Ⅰ | 必修 | |||
| 言語学Ⅱ | 必修 | |||
| 言語発達学 | 必修 | |||
| 基礎音声学 | 必修 | |||
| 音声学 | 必修 | |||
| 音声音響学 | 必修 | |||
| 聴覚心理学 | 必修 | |||
| 言語聴覚障害学概論 | 必修 | |||
| コミュニケーション技能演習 | 必修 | |||
| コミュニケーション障害演習 | 必修 | |||
| 言語聴覚障害診断学 | 必修 | |||
| 言語聴覚療法管理学 | 必修 | |||
| 失語症・高次脳機能障害学総論Ⅰ | 必修 | |||
| 失語症・高次脳機能障害学総論Ⅱ | 必修 | |||
| 失語症学Ⅰ(評価・診断) | 必修 | |||
| 失語症学Ⅱ(治療) | 必修 | |||
| 失語症・高次脳機能障害学演習 | 必修 | |||
| 高次脳機能障害学 | 必修 | |||
| 言語発達障害学総論 | 必修 | |||
| 言語発達障害学各論 | 必修 | |||
| 言語発達障害学Ⅰ(評価・診断) | 必修 | |||
| 言語発達障害学Ⅰ演習(評価・診断) | 必修 | |||
| 言語発達障害学Ⅱ(指導) | 必修 | |||
| 言語発達障害学Ⅱ演習(指導) | 必修 | |||
| 聴覚障害学総論 | 必修 | |||
| 聴覚機能評価学 | 必修 | |||
| 聴覚補償論(補聴器・人工内耳など) | 必修 | |||
| 小児聴覚障害学Ⅰ(評価・診断) | 必修 | |||
| 小児聴覚障害学Ⅱ(指導) | 必修 | |||
| 成人聴覚障害学(二重障害を含む) | 必修 | |||
| 発声発語障害学総論 | 必修 | |||
| 構音障害学Ⅰ(理論) | 必修 | |||
| 構音障害学Ⅱ(評価・診断) | 必修 | |||
| 構音障害学演習(治療) | 必修 | |||
| 流暢性障害学 | 必修 | |||
| 音声障害学 | 必修 | |||
| 摂食・嚥下障害学Ⅰ(理論・評価診断) | 必修 | |||
| 摂食・嚥下障害学Ⅱ(治療) | 必修 | |||
| 地域言語聴覚療法学 | 必修 | |||
| 言語聴覚障害学研究法 | 選択 | |||
| 言語聴覚障害基礎演習 | 必修 | |||
| 言語聴覚療法特論 | 必修 | |||
| 言語聴覚障害学特論(総括) | 必修 | |||
| 卒業研究 | 選択 | |||
| 見学実習 | 必修 | |||
| 評価実習 | 必修 | |||
| 総合実習 | 必修 |
※ 表記の科目は全課程の一部であり、このほかにも履修科目があります。